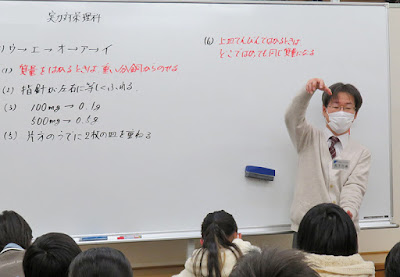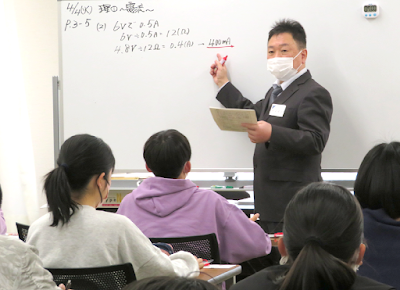理科の小ネタ

【 ジェイ教育セミナー網干南校 田邉 】 最近、理系の講師との間で、太陽系において、なぜ地球型惑星と木星型惑星が現在のような配置になっているのかが話題になりました。中3の皆さんはご存じのように、地球型惑星とは、岩石や金属でできた密度の大きな惑星、木星型惑星とは水素やヘリウムなどのような軽い物質でできた密度の小さな惑星です。なぜ太陽系では、水星、金星、地球、火星といった地球型惑星は、木星、土星などの巨大ガス惑星や、天王星などの巨大氷惑星といった木星型惑星よりも内側の軌道を公転しているのでしょうか。その理系の講師は、地球型惑星の材料となった岩石や金属の「ちり」は密度が大きいため、原始太陽がもたらす重力の影響によって、太陽の近くに引き寄せられたため、太陽の近くに地球型惑星ができたのだとして説明しており、知的な興味を掻き立てられました。 実は、この問題は太陽系の誕生と進化に関わるテーマで、天文学の最先端の研究分野の一つになっており、さまざまな仮説が提唱されています。おおまかに言うと、原始太陽が形成される過程で、これを覆っていた岩石や金属などの「ちり」でできた巨大な塊に回転運動が生じ、それが遠心力で外部にばらまかれることで「原始惑星系円盤」が生まれ、その中で惑星が生まれたとされています。地球型惑星と木星型惑星のちがいが生まれた原因としては、太陽の熱が原因となって、太陽から火星の公転軌道と木星の公転軌道の間にある「スノーライン」(つまり、氷の「ちり」が存在できるかどうかの境界線)までは氷のちりが存在できなかったためだと考えられています。 ですが、最近の観測で太陽系以外の惑星に関する研究が進み、中心の恒星の近くで木星のような巨大なガス惑星が公転していることが発見されています(「ホット・ジュピター」問題)。また、天文学者の間には、太陽系の誕生当時、木星と土星は現在の軌道よりも内側で誕生、その後、軌道が外側へと移って行ったとする説を提唱する者もおり、従来の説は大きく見直しを迫られています(ニュートン2014年7月号参照)。 このように、太陽系の誕生と進化という課題ひとつをとってみても、広大な未知の領域が広がっていることを考えると、現在の科学で分かっているのは、ごく一部にしか過ぎないということを痛感させられます。