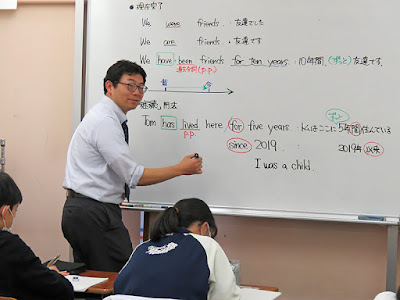歴史の話「隋、その他」

【 ジェイ教育セミナー大津校 中森 】 先日、京都文化博物館まで「大シルクロード展」を見に行ってきました。千年、二千年を経ているはずの文化財の中には鮮やかな色彩まで残っているものもあり、その華やかさに驚きました。保存状態の良さは、乾燥帯の風土ならではですね。 展示では、しばしば登場する「ソグド人商人」の語が印象に残りました。 私は最近、『南北朝時代―五胡十六国から隋の統一まで』(会田大輔)と『隋―「流星王朝」の光芒』(平田陽一郎)という2冊の新書を読んだのですが、その中にソグド人が登場していたのです。ソグド人は、当時のペルシャなどの西方と中国などの東方の架け橋となって活躍した民族です。 展示品を見ていると、千五百年ほど前の中国の混乱期を、歴史に翻弄されながら強く生き抜いた人々の姿が、実感を伴って浮かんできました。 さて、今回のテーマのひとつ、「隋」です。 この国名にピンとくる方は多いかと思います。聖徳太子について学ぶときに必ず出てくる「遣隋使」の、あの隋です。 唐などその後の王朝につながる「科挙」などの制度の原形を作ったり、黄河と長江をつないで余りある「大運河」開鑿という、にわかに信じられないほどの大土木工事を行ったりと、短命な割に歴史上のインパクトは大きい王朝です。 そうした大事業の立役者であり、それらを進める中で多くの民衆を苦しめたために、隋滅亡の原因となったのが、隋王朝二代皇帝の煬帝(ようだい)です。 この煬帝、悪い皇帝の代表格のように語られがちですが、単純な善悪では決められない、スケールの大きな人物です。(詩文をよくした文人皇帝でもあったそうです) ところでこの煬帝の悪評、中国の皇帝には割とありがちなことなのです。 というのも、ある王朝が滅んだ後に、次の王朝が、自身の正統性をアピールするために、前代の王朝と皇帝の悪行を記述した新しい歴史書を作る、というのが中国の伝統でした。 隋の場合は、次の唐王朝の時代に悪政を批判され、「楊広(ようこう)」という名前であった皇帝は、わざわざ「激しく民を苦しめる」という意味の漢字で「煬帝」と表記されたのです。 こうして、「煬帝」の悪評は千年の時を超えて現代までとどろきわたることになりました。近年、煬帝を再評価する機運が高まっている様子です。 のちの時代の風潮や社会によって評価が大きく変化するというのは、個人的に非常に...